なぜ君は本を読んでいるのに読解力が付かないのか
- johnny-osoro
- 2月24日
- 読了時間: 3分
本を読んでいるのに国語が苦手、という生徒は多い。かく言う自分も中高生の時は映画や本に常に触れていたが、国語、特に論説文を得意だと思えなかった。
こういうタイプの子は、同じ作品に繰り返し触れる経験が少ないのではないか、と思う。当時の自分も、小説でも映画でも、一度体験したらそれで終わりで、見返すことはなかった。
残念ながら、こういうやり方では作品を理解する力は付かないと思う。読解力を付けるには、もっとシンプルな方法がよい。つまり、「ひとつの作品に繰り返し触れる」という方法である。
そもそも、一つの作品を一度の体験で理解できるはずがない。例えば映画では、1つの作品を作るのに1~2年、場合によっては10年かかることもある。制作陣も100人単位に及ぶ。これだけの作り手側の思考・熱量が投入されたものを、ただ2時間座って見ることで全て吸収できる、と思う方がおかしいのかもしれない。
確かに、一度で理解した気になることはある。しかし、国語や英語などの言語系の分野が厄介なのは、自分が理解していない自覚を持ちづらい点だ。次のレベルに進んで初めて、それまでが如何に曖昧な理解だったかを知る。謙虚な気持ちで、実はわかっていないのではないか、と留意しておくことが大切だ。
大切なのは、一つの小説や映画を興味を持って何度も読んだり見たりすること。同時に、一つの作品に全力で対峙することだ。そうこうするうちに今まで見えなかったものが見えてくる。点と点が線で繋がる感覚を味わうはずだ。こうして理解の次元を上げていく経験を積む。こうして初めて、自分が理解していなかったことが理解できるようになる。これが読解力が付いた瞬間だと思う。
また、他人の助けを借りることもできる。文学批評というジャンルは作品を深く分析し、その手法を体系化する分野だ。批評理論の入門本などで、他の人が有名な作品をどう読んでいるのかを知ることは効果的だ。例えば『テクスト批評の実践―英語圏文学・映画・漫画』では、漫画『デスノート』の批評を読むことができる。
次に大切なのは、繰り返し見たいと思う文章や作品に出会うことだ。これは偶然に左右されるから、日頃から様々なものに触れ続けるしかない。結局、知的好奇心を持つ、ということである。
ここで、受験勉強として入試問題の文章に触れればよいのでは、と思う人もいるはずだ。しかし、いわゆる受験勉強では読解力は伸びにくいと僕は思っている。作品全体に触れることができず、どうしても生徒の焦点は設問の解法に行ってしまうからだ。
国語の受験勉強が無駄だ、という訳ではない。選択肢の切り方や記述答案の作り方は大切な技術である。しかし、包括的な「読解力」を付けたいなら、試験問題に正答するレベルを超えて、より深い理解の境地に達することを目指すべきだ。特に、文章を俯瞰する力=全体を構造化する力は、試験問題の様なブツ切りの文章では養いにくい。
「繰り返し」がポイントである。同じものに何度も触れ、理解度を上げていく経験を積むこと。そして、何度も触れられるような好きな作品と出会うために、好奇心を持つこと。これが読解力の秘訣だと思う。

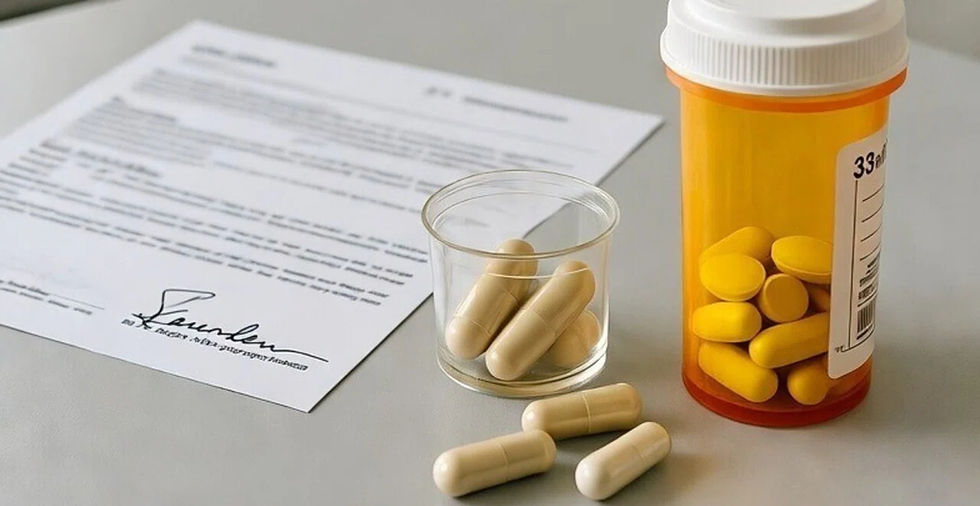


コメント